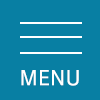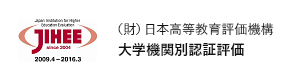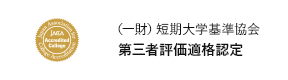ロカボってどうなのよ?
エネルギー産生栄養素と低炭水化物食 1)
人体が活動するために必要なエネルギーは、主として三大栄養素であるタンパク質(Protein),脂質(Fat),炭水化物(Carbohydrate)の代謝によって得られます。そしてこれらエネルギーに転換できる栄養素の比率をPFC比と呼び、食事摂取基準2020年版によると18〜29歳の場合、P: 13〜20%, F: 20〜30%,C: 50〜65%が設定されています。
しかし一部の生活習慣病は、これらの栄養素に対して正常な代謝を行うことができず各種臓器へ負担を抱えることとなり臓器不全を引き起こすことになります。そのため、一部の栄養素の摂取を制限することが食事療法として求められます。例えば、糖質代謝異常の結果生じるII型糖尿病などの場合は、糖質制限が有効となり、そのために推奨されているのが低炭水化物食となります。
炭水化物の機能と性質
炭水化物は化学的には糖質に分類されており、代表的なものはブドウ糖(D-グルコース)と呼ばれているものです。植物から動物まで目で捉えることのできる生命体から、目に見えない細菌に至るまで、地球上のほとんどがエネルギー源として利用できる物質です。
その化学的な性質は、水との親和性が強く、やや暴れん坊といった性質であり、近傍にある様々な物質に手当たり次第にちょっかいをかける、ちょっとしたナンパヤローな物質です。
その有り余るエネルギーを利用して生物は活動することができるわけですが、私たちの身近な所でも、鏡の製造(銀鏡反応),衣類の黄ばみ,ホットケーキの香ばしい焼き色,煮物の色付きなどの元となっています(これをメイラード反応と呼びます)。
糖尿病のメカニズム
このように、炭水化物のやんちゃぶりは容易に観察できるほどなのですが、当然のことながら私たちの体内でも発揮されてしまいます。ブドウ糖は通常血液中に 100 mg/dL 程度含まれているわけですが、これらが血液中や血管壁の細胞にやんちゃします。やんちゃされた細胞はちょっと動きにくくなり、機能が低下します。特に抹消の毛細血管には致命的に作用するため、壊死に至り合併症を引き起こす元となっています。
その結果産まれるのが、血液検査の項目にある HbA1c(ヘモグロビンA1c)という状態で、赤血球の重要なタンパク質であるHb(ヘモグロビン)というタンパク質が変化した結果です。赤血球はおよそ3ヶ月の寿命なので、HbA1cは過去3ヶ月の間に、どれだけブドウ糖にやんちゃされたのかを物語る指標となっており、全身の細胞がどれだけブドウ糖に冒されてきたのかを知ることができます。
通常は様々なホルモンや自律神経系により、このブドウ糖のやんちゃを嗜めているのですが、量が増えすぎると慣れもあり対処も甘くなってきます。この状態がII型糖尿病と呼ばれる病状です。
そのため、II型糖尿病もしくはそれに近い場合は、血糖が正常範囲となるような治療が施され、そこで推奨される食事療法が低炭水化物食の始まりとなっています。
低炭水化物食とLDLコレステロールと肥満
炭水化物というと近年はロカボ(ローカーボンハイドレート)ダイエットなどと持て囃されており注目されています。
実際に炭水化物を過剰に摂取した場合は、まずはグリコーゲンという形で肝臓や筋肉に蓄えられるのですが、それ以上の場合は肝臓で脂質に変換されてしまい、抹消の脂肪組織に送られ蓄積されます。
この時、血管を通って運ばれる途中の状態がLDLコレステロールであり、通称悪玉コレステロールと呼ばれるものです。そして脂肪組織で荷卸して肝臓に戻ってくるものがHDLコレステロールと呼ばれるものです。
私は授業中、このコレステロール(正式にはリポタンパク質と言います)をトラックに例えます。荷物である発泡スチロール(脂質)を大量に積んで各地に運ぶ状態をLDL,荷卸して戻ってくる状態の空のトラックをHDLと考えてもらうとわかりやすいと思います。
つまり、LDLが多い状態とは運ぶ荷物(脂質)が過剰な状態であり、より肥満へと至る課程と言い換えることができます。そのため、運ぶ荷物を減らしてあげるために、摂取する荷物を制限しよう=低炭水化物食という考え方となります。
低炭水化物食の効果
このように低炭水化物食はエネルギー摂取が過剰な場合には直接的な効果を発揮します。しかし、過剰ではない場合にはどうなのでしょうか?
食事摂取基準2020年版策定委員会報告書によると、減量効果は肥満症や過体重ではない場合、摂取栄養素の違いに意味はなく、総摂取エネルギー量の方が重要としています。また、HbA1cの低減効果も炭水化物15%未満では差異が認められなかったとしています。つまり、過度な低炭水化物食には効果は期待できないとされています。2)
その理由を考えるためには糖質代謝の仕組みを知る必要があります。糖質をエネルギーに変換する代謝は生物学的には「呼吸 (respiration)」と呼びます。
呼吸は解糖・TCAサイクル・酸化的リン酸化の3段階で進行し、この代謝は前段階が進まないと進行しない仕組みとなっています。解糖は糖が無ければ進みません。そしてTCAサイクルも解糖が進まないと止まります。
ここが大事なのが、TCAサイクルです。TCAサイクルは脂質を始めタンパク質などをエネルギーに変えると同時に、過剰な栄養素を脂質へと案内するなど、エネルギー代謝のジャンクションのような回路でもあります。つまり、どれだけ肥満状態で脂質が余っていようとも、糖質を摂取して解糖を働かせないと脂質を使うこともできない上に、送られる多くの物質が脂質へと変換されてしまいます。その結果、食事をしていないにも限らず高脂血症となり脂肪肝に至る場合もありえます。
ケトジェニック環境と飢餓 3,4)
この状態は飢餓と同じであり、一部はアセト酢酸(いわゆるケトン体と呼ばれ絶食状態や糖尿病患者で上昇する)と呼ばれるブドウ糖以上に反応性が高い物質へと変換され、脳のエネルギー源として利用されます。
この状態をケトジェニック環境と言いますが(まだ知見は多くありません)、これはそもそも飢餓に対応するための特別な代謝経路であり、基本的には省エネ用の緊急経路となっています。そのため短期には減量効果を期待できるかもしれませんが、全身でエネルギー利用を効率化するようになっており、長期に至るとかえって痩せにくい状態になってしまう可能性も示しています。
また国立がんセンター研究所のコホート研究では、過度な低炭水化物食は死亡リスクをあげることも示しており、低炭水化物食を手放しで歓迎できるものではありません。
低炭水化物食と知的活動 5)
また、つい最近(2022年1月)発表されて話題になったのがワーキングメモリ(記憶領域)への影響です。健康なマウスに低炭水化物高タンパク質食を摂取させると記憶機能を抑制する可能性があるというものです。
最初に挙げたように、低炭水化物食は元々健康ではない人たち向けに研究され、それに対する療養効果が認められてきました。一方で健常者を対象とした研究は世界的にも少ない上に、減量などとの関連が主となっています。このように日常生活との関連という意味で画期的な報告となっています。
これ自身はマウスが対象であるため、ヒトにそのまま外挿できるものではありませんが、飢餓に近い状態であると考えると頷ける気がします。マウスのような小動物の場合、飢餓であり危機的な状態であるほど、余計なことをあれこれ思い悩んで停滞するよりも、まずは直感に従い行動をする方が生存確率は高いのかも知れません。
1) 厚生労働省: 日本人の食事摂取基準(2020 年版) 2018年1月
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586553.pdf (2023/1/26日確認)
2) Van Elswyk ME, Weatherford CA, McNeill SH. : A Systematic Review of Renal Health in Healthy Individuals Associated with Protein Intake above the US Recommended Daily Allowance in Randomized Controlled Trials and Observational Studies. Adv Nutr 2018; 9: 404─18.
3) 西田 朱里, 宮本 潤基, 木村 郁夫: ケトン体(アセト酢酸)の受容体を介した脂質代謝アセト酢酸をリガンドとするGPCRsの発見, 化学と生物 2021; 59(6): 264-266.
https://katosei.jsbba.or.jp/view_html.php?aid=1438 (2023/1/26日確認)
4) 国立がん研究センターがん対策研究所予防関連プロジェクト: 多目的コホート研究(JPHC研究)からの成果報告-低炭水化物食と死亡リスクとの関連-
https://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/8641.html (2023/1/26日確認)
5) Takeru SHIMA, Tomonori YOSHIKAWA, Hayate ONISHI: Low-Carbohydrate and High-Protein Diet Suppresses Working Memory Function in Healthy Mice. J Nutr Sci 2022; 68(6): 527-532
https://doi.org/10.3177/jnsv.68.527
エネルギー産生栄養素と低炭水化物食 1)
人体が活動するために必要なエネルギーは、主として三大栄養素であるタンパク質(Protein),脂質(Fat),炭水化物(Carbohydrate)の代謝によって得られます。そしてこれらエネルギーに転換できる栄養素の比率をPFC比と呼び、食事摂取基準2020年版によると18〜29歳の場合、P: 13〜20%, F: 20〜30%,C: 50〜65%が設定されています。
しかし一部の生活習慣病は、これらの栄養素に対して正常な代謝を行うことができず各種臓器へ負担を抱えることとなり臓器不全を引き起こすことになります。そのため、一部の栄養素の摂取を制限することが食事療法として求められます。例えば、糖質代謝異常の結果生じるII型糖尿病などの場合は、糖質制限が有効となり、そのために推奨されているのが低炭水化物食となります。
炭水化物の機能と性質
炭水化物は化学的には糖質に分類されており、代表的なものはブドウ糖(D-グルコース)と呼ばれているものです。植物から動物まで目で捉えることのできる生命体から、目に見えない細菌に至るまで、地球上のほとんどがエネルギー源として利用できる物質です。
その化学的な性質は、水との親和性が強く、やや暴れん坊といった性質であり、近傍にある様々な物質に手当たり次第にちょっかいをかける、ちょっとしたナンパヤローな物質です。
その有り余るエネルギーを利用して生物は活動することができるわけですが、私たちの身近な所でも、鏡の製造(銀鏡反応),衣類の黄ばみ,ホットケーキの香ばしい焼き色,煮物の色付きなどの元となっています(これをメイラード反応と呼びます)。
糖尿病のメカニズム
このように、炭水化物のやんちゃぶりは容易に観察できるほどなのですが、当然のことながら私たちの体内でも発揮されてしまいます。ブドウ糖は通常血液中に 100 mg/dL 程度含まれているわけですが、これらが血液中や血管壁の細胞にやんちゃします。やんちゃされた細胞はちょっと動きにくくなり、機能が低下します。特に抹消の毛細血管には致命的に作用するため、壊死に至り合併症を引き起こす元となっています。
その結果産まれるのが、血液検査の項目にある HbA1c(ヘモグロビンA1c)という状態で、赤血球の重要なタンパク質であるHb(ヘモグロビン)というタンパク質が変化した結果です。赤血球はおよそ3ヶ月の寿命なので、HbA1cは過去3ヶ月の間に、どれだけブドウ糖にやんちゃされたのかを物語る指標となっており、全身の細胞がどれだけブドウ糖に冒されてきたのかを知ることができます。
通常は様々なホルモンや自律神経系により、このブドウ糖のやんちゃを嗜めているのですが、量が増えすぎると慣れもあり対処も甘くなってきます。この状態がII型糖尿病と呼ばれる病状です。
そのため、II型糖尿病もしくはそれに近い場合は、血糖が正常範囲となるような治療が施され、そこで推奨される食事療法が低炭水化物食の始まりとなっています。
低炭水化物食とLDLコレステロールと肥満
炭水化物というと近年はロカボ(ローカーボンハイドレート)ダイエットなどと持て囃されており注目されています。
実際に炭水化物を過剰に摂取した場合は、まずはグリコーゲンという形で肝臓や筋肉に蓄えられるのですが、それ以上の場合は肝臓で脂質に変換されてしまい、抹消の脂肪組織に送られ蓄積されます。
この時、血管を通って運ばれる途中の状態がLDLコレステロールであり、通称悪玉コレステロールと呼ばれるものです。そして脂肪組織で荷卸して肝臓に戻ってくるものがHDLコレステロールと呼ばれるものです。
私は授業中、このコレステロール(正式にはリポタンパク質と言います)をトラックに例えます。荷物である発泡スチロール(脂質)を大量に積んで各地に運ぶ状態をLDL,荷卸して戻ってくる状態の空のトラックをHDLと考えてもらうとわかりやすいと思います。
つまり、LDLが多い状態とは運ぶ荷物(脂質)が過剰な状態であり、より肥満へと至る課程と言い換えることができます。そのため、運ぶ荷物を減らしてあげるために、摂取する荷物を制限しよう=低炭水化物食という考え方となります。
低炭水化物食の効果
このように低炭水化物食はエネルギー摂取が過剰な場合には直接的な効果を発揮します。しかし、過剰ではない場合にはどうなのでしょうか?
食事摂取基準2020年版策定委員会報告書によると、減量効果は肥満症や過体重ではない場合、摂取栄養素の違いに意味はなく、総摂取エネルギー量の方が重要としています。また、HbA1cの低減効果も炭水化物15%未満では差異が認められなかったとしています。つまり、過度な低炭水化物食には効果は期待できないとされています。2)
その理由を考えるためには糖質代謝の仕組みを知る必要があります。糖質をエネルギーに変換する代謝は生物学的には「呼吸 (respiration)」と呼びます。
呼吸は解糖・TCAサイクル・酸化的リン酸化の3段階で進行し、この代謝は前段階が進まないと進行しない仕組みとなっています。解糖は糖が無ければ進みません。そしてTCAサイクルも解糖が進まないと止まります。
ここが大事なのが、TCAサイクルです。TCAサイクルは脂質を始めタンパク質などをエネルギーに変えると同時に、過剰な栄養素を脂質へと案内するなど、エネルギー代謝のジャンクションのような回路でもあります。つまり、どれだけ肥満状態で脂質が余っていようとも、糖質を摂取して解糖を働かせないと脂質を使うこともできない上に、送られる多くの物質が脂質へと変換されてしまいます。その結果、食事をしていないにも限らず高脂血症となり脂肪肝に至る場合もありえます。
ケトジェニック環境と飢餓 3,4)
この状態は飢餓と同じであり、一部はアセト酢酸(いわゆるケトン体と呼ばれ絶食状態や糖尿病患者で上昇する)と呼ばれるブドウ糖以上に反応性が高い物質へと変換され、脳のエネルギー源として利用されます。
この状態をケトジェニック環境と言いますが(まだ知見は多くありません)、これはそもそも飢餓に対応するための特別な代謝経路であり、基本的には省エネ用の緊急経路となっています。そのため短期には減量効果を期待できるかもしれませんが、全身でエネルギー利用を効率化するようになっており、長期に至るとかえって痩せにくい状態になってしまう可能性も示しています。
また国立がんセンター研究所のコホート研究では、過度な低炭水化物食は死亡リスクをあげることも示しており、低炭水化物食を手放しで歓迎できるものではありません。
低炭水化物食と知的活動 5)
また、つい最近(2022年1月)発表されて話題になったのがワーキングメモリ(記憶領域)への影響です。健康なマウスに低炭水化物高タンパク質食を摂取させると記憶機能を抑制する可能性があるというものです。
最初に挙げたように、低炭水化物食は元々健康ではない人たち向けに研究され、それに対する療養効果が認められてきました。一方で健常者を対象とした研究は世界的にも少ない上に、減量などとの関連が主となっています。このように日常生活との関連という意味で画期的な報告となっています。
これ自身はマウスが対象であるため、ヒトにそのまま外挿できるものではありませんが、飢餓に近い状態であると考えると頷ける気がします。マウスのような小動物の場合、飢餓であり危機的な状態であるほど、余計なことをあれこれ思い悩んで停滞するよりも、まずは直感に従い行動をする方が生存確率は高いのかも知れません。
1) 厚生労働省: 日本人の食事摂取基準(2020 年版) 2018年1月
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586553.pdf (2023/1/26日確認)
2) Van Elswyk ME, Weatherford CA, McNeill SH. : A Systematic Review of Renal Health in Healthy Individuals Associated with Protein Intake above the US Recommended Daily Allowance in Randomized Controlled Trials and Observational Studies. Adv Nutr 2018; 9: 404─18.
3) 西田 朱里, 宮本 潤基, 木村 郁夫: ケトン体(アセト酢酸)の受容体を介した脂質代謝アセト酢酸をリガンドとするGPCRsの発見, 化学と生物 2021; 59(6): 264-266.
https://katosei.jsbba.or.jp/view_html.php?aid=1438 (2023/1/26日確認)
4) 国立がん研究センターがん対策研究所予防関連プロジェクト: 多目的コホート研究(JPHC研究)からの成果報告-低炭水化物食と死亡リスクとの関連-
https://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/8641.html (2023/1/26日確認)
5) Takeru SHIMA, Tomonori YOSHIKAWA, Hayate ONISHI: Low-Carbohydrate and High-Protein Diet Suppresses Working Memory Function in Healthy Mice. J Nutr Sci 2022; 68(6): 527-532
https://doi.org/10.3177/jnsv.68.527